小型犬は愛らしく扱いやすいため人気がありますが、犬種ごとに性格や特徴が異なるため、どの種類を選ぶか迷う人が多くいます。この記事では、さまざまな小型犬の特徴や性格、選び方をまとめました。最後まで読めば、小型犬の迎え方や適切な飼育方法がわかります。
小型犬を飼う際には、ライフスタイルや住環境に合わせて犬種を選ぶことが重要です。それぞれの特徴を理解して、自分に合った小型犬を迎え入れましょう。
人気の小型犬の種類

人気の小型犬の種類は、以下のとおりです。
- トイ・プードル
- チワワ
- ミニチュア・ダックスフンド
- ヨークシャー・テリア
- ポメラニアン
トイ・プードル
トイ・プードルは小さな体格で、体重は約2〜4kg、体高は約25〜28cmです。毛色は白や黒、茶、グレーなどさまざまで、巻き毛に特徴があります。抜け毛が少ないので、アレルギーを持つ人にも適しています。性格は賢く、訓練しやすく、人懐っこいのが特徴です。運動量は中程度で、室内飼いに適しています。
平均寿命は約14〜18年で、目や耳の病気に注意が必要です。グルーミングには手間がかかります。毛が伸び続けるので、定期的にトリミングを行う必要があります。吠える傾向があるので、適切なしつけも重要です。子犬の価格は15〜30万円程度です。
» トイプードルの性格の特徴や飼い方を徹底解説
チワワ
チワワはメキシコ原産の犬種であり、体重が約1.5〜3kgと世界最小の犬種の一つとして知られています。チワワの魅力は以下のとおりです。
- 長寿(約12〜20年)
- 短毛と長毛の2タイプ
- 警戒心が強く番犬として優秀
- 忠誠心の強さ
- 飼い主によく懐く性格
寒さに弱いので、防寒対策が必要です。目が飛び出ているため、眼球のけがに注意してください。歯が小さく歯石がつきやすいので、口腔ケアが重要です。膝蓋骨(しつがいこつ)脱臼のリスクがあるので、適度な運動管理も欠かせません。運動量が少なめなので、アパートでも飼育できますが、吠える傾向があるため近隣への配慮が大切です。
ミニチュア・ダックスフンド

ミニチュア・ダックスフンドは体長約20~25cm、体重約3.5~5kgと小柄で、短足で胴長の特徴的な体型をしています。ミニチュア・ダックスフンドの魅力は、以下のとおりです。
- 賢く、飼い主に懐きやすい性格
- 好奇心旺盛で活発な性質
- 警戒心が強く、番犬として優秀
毛色は単色や2色、3色とさまざまで、毛質は短毛や長毛、ワイヤーヘアの3種類があります。寿命は約12~16年と比較的長めです。吠える傾向があるため、注意が必要です。脊椎関連の健康問題にも気をつけてください。しつけはやや難しいですが、子どもや他のペットとも仲良く過ごせます。
ヨークシャー・テリア
ヨークシャー・テリアは、長くシルキーな被毛が特徴的な犬種です。体重は約2.3〜3.2kgと小さく、室内飼いに適しています。寿命は約12〜15年で、性格は活発で賢く、忠誠心が強いのが特徴です。飼い主との強い絆を形成する傾向があります。警戒心が強く番犬としても優秀なため、吠える傾向があります。
アレルギーを起こしにくいのも魅力です。社交的で子どもとの相性が良く、散歩や室内遊びで十分な運動量を確保できます。小さな体格のため、けがには注意が必要です。長い被毛のグルーミングに手間がかかるので、定期的なケアが欠かせません。
ポメラニアン
ポメラニアンはドイツ原産のスピッツ系の犬種で、体重は約1.8〜3.5kgと小さめです。長くて豊かな被毛が特徴で、美しい毛並みを持ちますが、毛の手入れには時間がかかります。性格は活発で知能が高く、しつけがしやすいのが特徴です。警戒心が強く番犬としても優秀ですが、吠える傾向があります。
ポメラニアンは室内飼いに適しており、寿命は約12〜16年です。オレンジやクリーム、ブラックなどのカラーが人気です。健康面では、膝蓋骨脱臼や気管虚脱に注意してください。子犬の価格は、約20〜40万円が目安になります。
珍しい小型犬の種類

珍しい小型犬の種類は、以下のとおりです。
- ノーリッチ・テリア
- スキッパーキ
ノーリッチ・テリア
ノーリッチ・テリアは、イギリス原産の珍しい小型犬です。体重は約5~5.5kg、体高は約25cmで、コンパクトな体格をしています。短い足と長い胴体が特徴的です。毛色は赤や黒タン、グリズル、小麦色などがあり、毛質は硬くてワイヤー状です。性格は活発で勇敢、自信に満ちています。
知的で訓練しやすいので、初心者にもおすすめです。警戒心が強いため、番犬としても優秀です。子どもや他のペットとも仲良く過ごせます。寿命は約12~15年で、週に2~3回のブラッシングが必要です。運動量は中程度で、毎日の散歩や遊びが欠かせません。アレルギー反応が少ない犬種としても知られています。
スキッパーキ
スキッパーキは、ベルギー原産の珍しい小型犬です。体重は約6~8kg、体高は約25~33cmと、小柄な体格に特徴があります。毛色は黒や茶、フォーン(薄茶)が一般的で、立ち耳で三角形の耳が印象的です。知的で活発な性格ですが、警戒心が強いため十分なしつけが必要になります。
飼い主に忠実で、家族思いな面もあります。運動量が多いため、定期的な散歩や遊びが欠かせません。賢い犬種なので、しつけがしやすい特徴があります。寿命は約15~20年と長く、アレルギー反応が少ない犬種です。毛の手入れは比較的簡単です。
性格別に見る小型犬の種類

小型犬の性格は、以下の3タイプに分けられます。
- 活発で遊び好きな小型犬
- おとなしくて飼いやすい小型犬
- 社交的で人懐っこい小型犬
活発で遊び好きな小型犬
活発で遊び好きな小型犬は、好奇心旺盛な性格をしています。代表的な犬種は、以下のとおりです。
- ジャック・ラッセル・テリア
- パピヨン
- ミニチュア・ピンシャー
- シェットランド・シープドッグ
- ウェルシュ・コーギー
遊びや運動が大好きで、運動量が多いため、毎日の散歩やボール遊びなどで十分に体を動かす機会を設けましょう。適切な運動は、犬の身体的・精神的な健康維持に役立ちます。知的な犬種が多いので、トレーニングやしつけにも積極的に取り組みましょう。犬の脳の活性化に効果があります。
おとなしくて飼いやすい小型犬

おとなしくて飼いやすい小型犬は、初心者や忙しい人に適しています。具体的な犬種は、以下のとおりです。
- シーズー
- 温厚で人懐っこい性格です。長い被毛のお手入れは必要ですが、散歩をそれほど必要としないため、室内で過ごす時間が長い人にも向いています。
- マルチーズ
- 穏やかで愛らしい性格の持ち主です。小柄で扱いやすく、家族との時間を大切にする犬種と言えます。
- パグ
- 温和でフレンドリーな性格です。短毛種なのでグルーミングの手間が少なく、運動量も控えめなため、初心者でも飼いやすい犬種です。
あまり吠えず、運動量も少ないので、アパートやマンションでの飼育に適しています。キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルやビション・フリーゼも、おとなしくて飼いやすい小型犬です。ただし個体差があるので、実際に会って相性を確認しましょう。
社交的で人懐っこい小型犬
社交的で人懐っこい小型犬は、人との触れ合いを好み、新しい人や環境にも順応しやすい特徴があります。代表的な犬種は、以下のとおりです。
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
- パピヨン
- マルチーズ
- シーズー
- ビション・フリーゼ
家族はもちろん、来客や見知らぬ人にも優しく接することが可能です。社交的な小型犬を飼うことで、飼い主の生活にも良い影響があります。散歩中に他の犬や人と出会う機会が増え、コミュニケーションの輪が広がります。社交的な性格を持つ犬種でも、適切なしつけと社会化は必要です。
自分に合った小型犬の選び方

小型犬を選ぶ際のポイントは、以下のとおりです。
- ライフスタイルに合わせて選ぶ
- 家族構成や住む環境に合わせて選ぶ
ライフスタイルに合わせて選ぶ
小型犬を選ぶ際には、ライフスタイルに合った犬種を選びましょう。仕事が忙しく在宅時間が短い人は、手がかからない犬種や1人で留守番ができる犬種を選ぶのがおすすめです。散歩や運動に十分な時間をかけられない人は、運動量の少ない犬種が適しています。
旅行や外出が多い人は、小さめの犬種を選ぶと移動が楽になります。犬の世話にかけられる時間が限られている人は、毛のケアが比較的簡単な犬種がおすすめです。朝型の人は朝の散歩を楽しめる活発な犬種、夜型の人はおとなしめの犬種が適しています。
家族構成や住む環境に合わせて選ぶ
以下の家族構成や環境に合ったおすすめの小型犬を紹介します。
- 子どもがいる家庭
- 温厚な性格の犬種がおすすめです。トイ・プードルやキャバリア・キング・チャールズ・スパニエルなどは忍耐強く、子どもと相性が良いのが特徴です。
- 高齢者がいる家庭
- 世話が簡単な犬種を検討しましょう。チワワやヨークシャー・テリアなどは、運動量が少なく、手入れも簡単です。
- アパート・マンション
- シーズーやマルチーズなど、吠え声の少ない犬種をおすすめします。
- 庭付きの一戸建て
- 運動量の多い犬種も選択肢の一つです。ジャック・ラッセル・テリアやミニチュア・シュナウザーなどが適しています。
- アレルギーがある家族
- ビション・フリーゼやプードルなど、アレルギーを起こしにくい犬種を考えましょう。
- 留守がちな家庭
- 柴犬やボストン・テリアなど、独立心があり、比較的1人で過ごせる犬種を検討しましょう。
近隣との関係を考慮し、騒音やにおいの少ない犬種を選ぶことも大切です。パピヨンやイタリアン・グレーハウンドなどはにおいが少なく、静かな犬種としておすすめです。
小型犬の迎え方

小型犬を迎える方法は、以下の3つがあります。
- ブリーダーから迎える
- 保護犬を迎える
- ペットショップから迎える
ブリーダーから迎える
ブリーダーを選ぶ際には、信頼できる相手を慎重に見極めることが大切です。評判の良いブリーダーを探し、直接会って話をしましょう。親犬の健康状態や性格を確認すると、子犬の将来の姿をイメージできます。子犬の成長環境や社会化の状況を確認しましょう。
適切な環境で育てられた子犬は、将来的に問題行動を起こしにくくなります。子犬の健康状態を知るうえで、予防接種や健康診断の記録は貴重な情報です。契約内容や保証についても確認しましょう。正式な契約書を交わし、健康保証や返金規定を確認することが大切です。子犬の引き渡し時期も確認しましょう。
早すぎる引き渡しは、子犬の健康や社会性の発達に悪影響を与える可能性があります。ブリーダーの施設や飼育環境の見学をおすすめします。実際に目で見て確認すると、より安心して子犬を迎えることが可能です。子犬と実際に触れ合い、相性を確認することも大切です。
保護犬を迎える

保護犬は、信頼できる保護団体やシェルターを通じて迎えましょう。自分の生活環境に合った犬を選ぶために、保護犬の性格や健康状態の事前確認が大切です。面会や試し飼いを行い、相性を確認することも重要です。保護犬を迎える際には、以下の点に注意しましょう。
- 必要な手続きや費用
- 心理的ケア
- 新環境への適応
忍耐強く、愛情を持って接することが大切です。保護犬の過去を受け入れ、新しい生活を一緒に築くことで、かけがえのない絆をつくれます。必要に応じて、専門家のアドバイスを受けることも有効です。
ペットショップから迎える
ペットショップでは、さまざまな種類の小型犬を一度に見比べられるので、自分に合った犬を見つけやすくなります。犬の性格や特徴、飼育方法について教えてもらえるので、初心者でも安心です。必要な用品をその場で購入できるのもポイントです。フードやケージ、首輪、リード、おもちゃなどの犬用品を一緒に選べます。
健康診断済みで、予防接種も完了している犬を販売しているペットショップが多いため、新しい家族を迎える際の不安を軽減できます。購入後のサポートやアフターケアが充実している場合もあり、困ったときに相談が可能です。即日引き取りできる場合が多いですが、十分に検討してから迎え入れましょう。
小型犬を飼育する際のポイント

小型犬の飼育には、以下の特別な配慮が必要です。
- 小型犬に合ったしつけをする
- 食事と運動を適切に管理する
- 定期健診を受ける
小型犬に合ったしつけをする
小型犬は集中力が続きにくいので、短時間で頻繁にトレーニングを行うのがおすすめです。1回のトレーニングは5〜10分程度にし、1日に数回実施しましょう。小型犬は褒められることが大好きなので、良い行動をしたときは褒めてあげてください。おやつや声かけ、撫でるなどの方法で褒めると効果的です。
小型犬は大きな声や荒い態度に怯えやすいので、優しく穏やかな声と態度でコミュニケーションを取ることも大切です。お座りや伏せ、待てなどの簡単な命令から練習を始めましょう。さまざまな人や環境に慣れさせ、社交的で落ち着いた犬に育てることが大切です。しつけの際、甘やかしすぎには注意してください。
食事と運動を適切に管理する

小型犬の体格に合わせた適量の食事を与え、高品質で栄養バランスの取れたドッグフードを選びましょう。1日2〜3回に分けて食事を与え、おやつは全体の食事量の10%以下に抑えることが大切です。毎日の散歩は15〜30分程度を目安に行い、室内でも適度な運動や遊びの時間を設けましょう。
食事量と運動量のバランスを取ることで、肥満を防げます。過度な運動は控え、犬の体調や年齢に合わせて調整することが重要です。食後すぐの激しい運動は控えてください。健康維持のため、水分補給も忘れずに行いましょう。
定期健診を受ける
年に1〜2回の定期健診を受けると、病気の早期発見・早期治療につながります。小型犬は体が小さいため、健康状態の変化に気づきにくい場合があります。実施可能な検査や処置は、以下のとおりです。
- 血液検査
- 尿検査
- 予防接種
- 歯石除去
- 爪切り
定期健診は、獣医師との信頼関係を築く機会にもなります。愛犬の年齢や健康状態に応じた適切なケアを受けることが可能です。
» 小型犬の年齢を人間換算でチェック!健康管理を徹底解説
まとめ
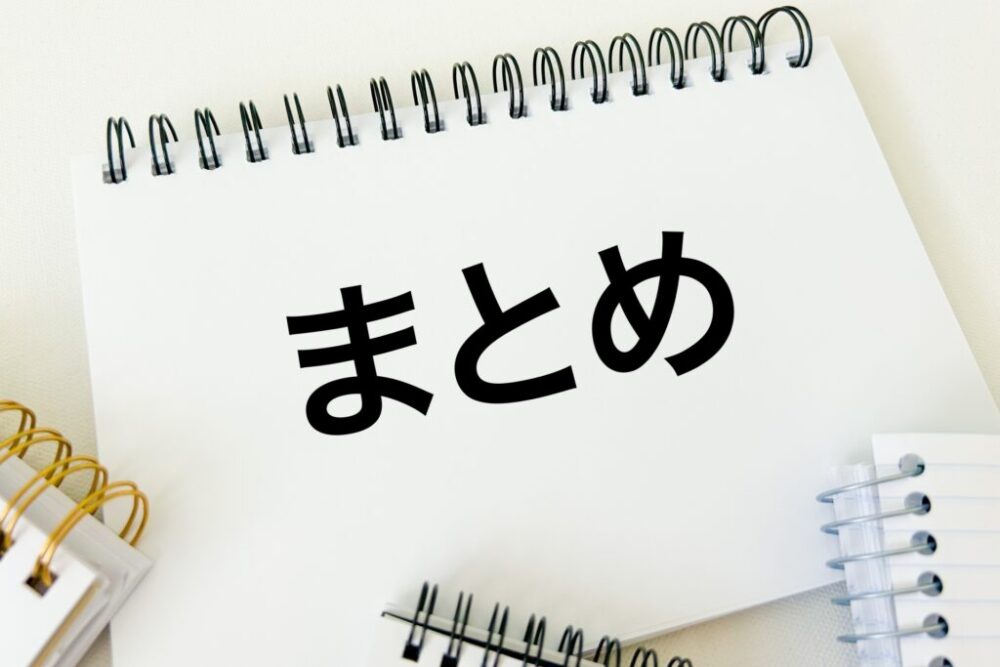
小型犬を飼うことは、多くの喜びと責任を伴います。小型犬は個性豊かで、飼い主との深い絆を築けます。小型犬を迎える前に、ライフスタイルや家族構成に合った犬種を選ぶことが重要です。人気の犬種だけでなく、珍しい犬種を検討するのも選択肢です。犬の性格も考慮に入れると、相性の良い犬を見つけられます。
犬を迎える方法には、ブリーダーや保護団体、ペットショップなど、さまざまな方法があります。それぞれのメリットとデメリットを理解し、自分に合った方法を選びましょう。


